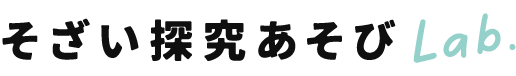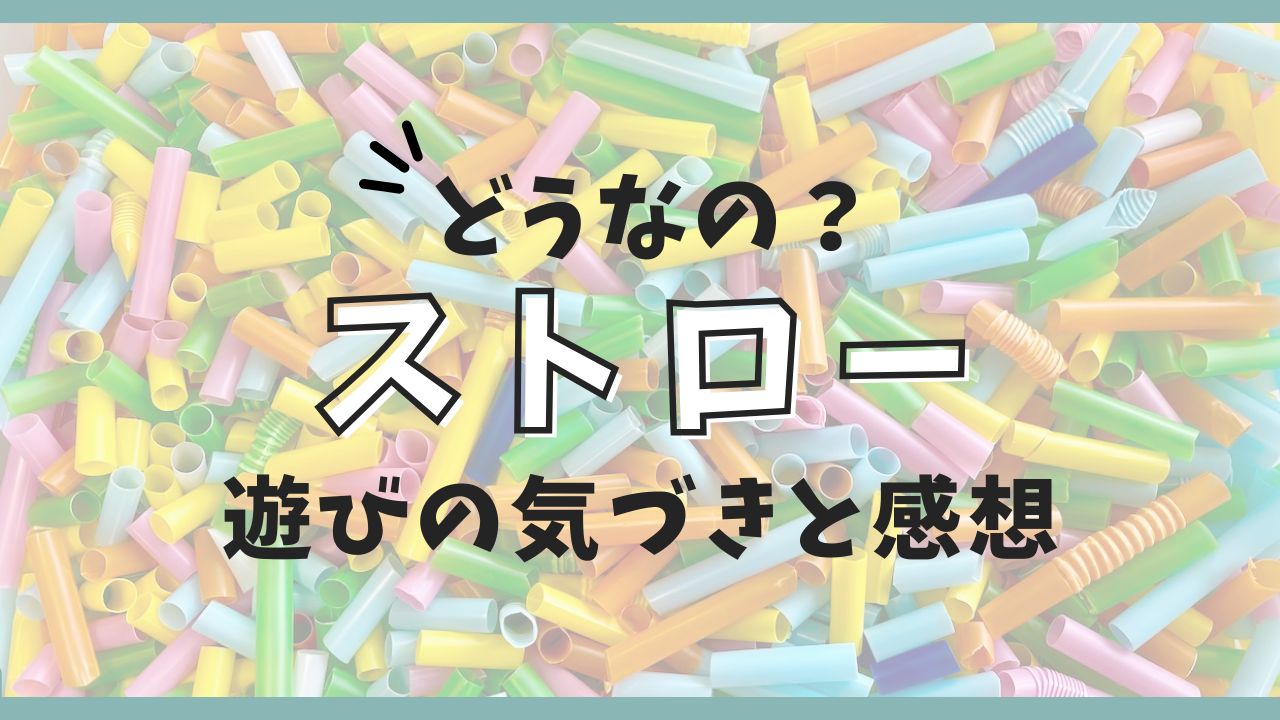先日、研修会にて講師を務めさせていただきました すみのえ幼稚園様より、ご参加いただきました先生方の貴重な気づきとご感想をいただきました。
とても私自身の参考になり、また、ストローの遊びを取り入れてみたいけれど…と気になっている先生方にも、ご参考いただけるのではと思いますので、ここに記録として残したいと思います。
その時の遊びの様子も、ぜひご覧ください。

研修会では、ストローでの遊びの体験のほか、次のようなお話をしています。
- ・ストローの特徴、メーカーごとの素材比較、購入先や費用
- ・使用する小道具の準備方法、注意点、購入先や費用など
- ・素材の保管や保育実践での取り組み方
それから「そざい探究あそびの心得」などなど、お話もさせていただいております。
「 子ども主体 」の遊びについて

子ども主体の捉え方の変化

子ども主体というと「子ども自らに気づいて欲しいな」という思いや、「これは誘導かな…?」と迷うことが多くありますが、保育者からの提案と実践がまず子どもの経験となり、さらに日常的に遊びに取り組むことで、その先に主体的に遊ぶ子どもの姿が見えてくるのだなとわかりました。
提案やヒントの必要性

「大人からの提案やヒントが必要」という言葉は、自分の保育に対する安心に繋がりました。
主体性を育む関わり

自園でも主体性保育を取り入れていて、子どもの気づきや発見を大切にしていますが、子どもの知識や経験を広げるために大人からの提案やヒントは必要であると改めて感じました。子どもが表現を楽しめるような大人からの関わり方を意識していきたいです。
桐嶋より
私自身がいろんな場所で先生や子どもたちと出会う中で、遊びの中での子どもの主体性というものの捉え方を悩まれている先生が多くいらっしゃると感じています。
すみのえ幼稚園の先生方がこれまで行なってこられた、子どもへの働きかけや、子どもとの関わり方について、「安心に繋がった」「再確認できた」と思っていただけたのでしたら、嬉しく思います。今後もう少しこの点を、私の研修会でも掘り下げてみてもいいのかなと勉強になりました。ありがとうございます。
ストロー遊びを体験して

子どもを見る視点

素材に触れて遊ぶ中で、一人ひとり探究したいことが異なることを知り、子どもそれぞれに“感じたもの”を広げてあげることに着目できました。つい、どうやって遊ぶかと1から10までの流れを考えがちですが、子どもが何を感じているか?に着目すると、遊びの広げ方もその時々で変わってくると思いました。
先生同士の学び合い

・周りの先生たちがやっていることがとても新鮮で、自分以外の遊びの発想やアイデアを得ることができ学びになりました。
・素材を手に取って遊び、実践をもとに行う研修は、先生たちと楽しみながらいろんな感想を共有したり、ワクワクして、子どもの気持ちや立場になってさまざまなことを感じながら学ぶことができました。
問いかけや言葉がけについて

大人からの問いかけにより、感じたことや気づいたことを言語化して伝え合う場面について、これはどの遊びでも大切にしていきたいことだと思いました。 保育者からの問いかけの内容によっても、子どもが考えるきっかけをつくり、五感が磨かれるので、問いかけの内容を意識していきたいです。
実践への活かし方

・ストローを使ったことはあるが、切って終わりになってしまうことが多かった。今回の体験の中では、それぞれの好きな楽しみ方が同時にできるのがよかったので、自分のクラスに合う楽しみ方を考えてみたい。
・トースターを使ったとき、偶然の産物が面白いなぁと思った。安全面に配慮し、子どもの「やってみたい!」「こうしてみたい」を叶えて、子どもたちの楽しい経験になればと思いました。
使用した量をどう思う?


2500本って多いのではないかと思いましたが、実際に体験すると、この量があったからここまで楽しめたと気づきました。たくさんのストローにただ触れているだけで楽しく、黙々と集中できました。普段、コーナーを分けているので素材ごとに区別して遊ぶようにしてしまっていたり、ぴったりの数やギリギリの数で遊ぶことが増えていたと思い返しました。

これまでストローで「製作」を行ったことはあっても、「遊び」は行っていませんでした。大量のストローに、大人の私でさえワクワクしたので、子どもならもっとドキドキ ワクワクするだろうと思いました! まずは「素材で遊ぶことが楽しい!」と思えるのも、子どもにとって大切な経験だなぁと思いました。
桐嶋より
最近は何を買うにも高くなり、私もコスト面を考えます。ですが、こうして量や種類が多くある方が興味のきっかけになる素材もあるため、そざい探究あそびとしては今後も量や種類を用意することを続けていきたいです。
ただし、その素材を時間をかけてさいごまで使いきるという さまざまな活用法も、今後は積極的に考えていかなければと思っています。今後の遊びの中で、先生方が見つけた新しい楽しみ方と活用法も、ぜひシェアしてくださいね!
今後の実践について
子どもや保護者との楽しみ方

・保護者参加の行事でも楽しめそうだと思いました。
・今、子どもたちの間でアイドルごっこが流行っているので、ストローをアクセサリーづくりなどに活かしてみたいと思います。
環境づくり

・素材コーナーに取り入れ、子どもが多様な素材の使い方を知ることに繋げていきたいです。
・透明容器への素材保管は、中身が見えて片付けの際にもわかりやすい。子どもたちが素材を“使いたい”と思える工夫をしていきたいです。
発達段階に応じた関わり

・子どもが自由に遊べるように材料を揃えたり、環境を整えてきましたが、年少の子どもたちには使い方を示したり、一緒に遊んで「やってみたい!」と思えるきっかけづくりを意識的に行なっていきたいです。
・年長クラスは細かい作業にも取り組めるので、アイロン、トースターを使って作品づくりに挑戦してみたいです。
素材との向き合い方

・ストローをきっかけに、身近なもので他にはどんな素材で遊ぶことができるのかを考えていきたいです。
・製作だけでなく、素材を感覚的に楽しむことも伝えたいと思った。
新たな発見
実践のヒントや工夫の発見

・床にたくさん広げたストローをどうやって片付けるかなど、実際に子どもと実践する時についても知ることができました。
・自分の保育環境で、使い方の約束を設けるかどうかに悩むことがあったので、「子どもの姿や遊び方により、最低限のルールは設ける」という話は、指標の1つとして参考にしたい考えだと思います。
・視覚的に子どもの好奇心を刺激できるように、素材の色を揃えたり、サンプルを飾ったりするのはいいなと思いました。
・素材の購入先や金額など細かいことも教えていただき、保育実践のハードルがグンと下がりました。
考え方の変化と安心感

子どもとの遊びの心構えを教えてもらい、「なるほど!」という発見や「これでいいんだ!」と安心する内容がたくさんありました。
まとめ
先生方の声から見えてきたもの
私が教える研修ではなく、先生同士が自ら楽しんで学び合う姿がとても印象的だった、すみのえ幼稚園の皆さま。
一人ひとりの先生が学びを受けるだけでなく、子どもたちの普段の姿を思い浮かべながら、今後どうこの遊びに取り組んでいこうかと真剣に考えてくださいました。
私も研修だけで終わりというのは寂しいので、取り組みの様子を今後も教えていただけますことを、とても楽しみにしています。
すみのえ幼稚園の皆さま、お忙しい中で、貴重なご感想や気づきをいただきありがとうございました。
▼ ご協力園